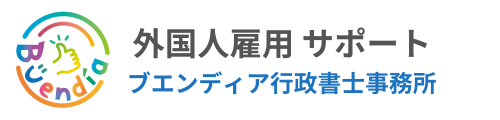建設業で外国人を雇用する方法|各要件及び注意点を解説
近年、日本の建設業界では人手不足が深刻化しており、外国人労働者の採用が注目されています。しかし、外国人を雇用する際には、在留資格や手続き、労働環境の整備など、さまざまな点に注意が必要です。本記事では、建設業で外国人を雇用するための方法や注意点について詳しく解説します。
建設業における外国人労働者の現状
日本の建設業界では、高齢化や若年層の減少により、人手不足が深刻化しています。この状況を受け、外国人労働者の受け入れが進んでいます。特に、技能実習生や特定技能制度を利用した外国人労働者の数は増加傾向にあります。
そして、2023年12月末の「建設業」全体における外国人労働者数は、144,981人、うち技能実習が88,830人、うち特定技能が24,463人となっております。
現在の奴隷制度と言われている技能実習ですが、実態としては非常に多くの外国人が就労している状況で、特定技能試験が非常に難関であることを考えると、技能実習優位の形は、今後も継続することが予想されます。

ビザの理解が重要
建設業で外国人材を雇用する場合には、ビザの知識は必須です。
外国人に従事してもらう業務内容に対してビザの種類が厳格に定められており、これに違反した場合不法就労助長罪で、企業が罰せられる可能性があります。
これについては、悪質な有料職業紹介事業者に騙されて、知らずに雇用してしまった場合でも、罪を免れることができなくなっているので、外国人を雇用する際には注意が必要なのです。
建設業界で働くことができるビザ
建設業界で働くことできるビザは以下のとおりです。
| ビザの種類 | ビザの内容 | 想定されている業務 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 主に大学卒業者を対象にした、いわゆるホワイトカラー職種のビザ | 施工管理等の工事責任者が想定されており、原則現場作業はできません。 |
| 特定活動46号 | 日本の大学または大学院を卒業し、日本語能力試験N1等に合格した方向けの通訳及び管理にかかるビザ | 現場での通訳業務、工事現場にかかるあらゆる業務に従事可能。もっとも、現場作業だけに従事させることは想定されていません。 |
| 技能実習 | 現場作業を行うことができるビザで、送り出し機関及び監理団体を通さなければいけないことが特徴 | あらかじめ定めた技能実習計画に沿って業務を行うことになります。 |
| 特定技能 | 技能実習の上位概念であり、即戦力人材として現場作業を行うことができるビザ、外国人に対する「支援」が必須であることが特徴 | 現場で様々な業務を行うことが可能となっています。ただし、単純作業のみに従事させることはできません。 |
| 身分系ビザ (永住・定住・配偶者) | 仕事内容に制限のないビザで、日本人と同じように働くことが可能 | 業務に制限はありません。 |
| 特定活動9号 (インターン) | 海外の大学と提携し、教育課程の一部として働くことができるビザ | あくまで大学教育の一貫であることから、現場作業のみに従事させることは想定されていません。 |
外国人に任せる業務が何なのかによって、募集するビザが異なるので、注意してください。

業務内容とビザの関係
外国人を雇用する際に一番大事なことが業務内容の確定です。
以下簡易的に建設業界で考えられる業務内容とビザの関係性を記載しました。
| 現場作業 | 現場監督 | 技術監督 | 品質管理責任者 | 施工管理技士 | 設計 | 調査・検査・測量 | プロジェクトマネージャー | 工程等管理責任者 | |
| 技術・人文知識・国際業務 | 原則不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 特定活動46号 | 条件付で可? | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 技能実習 | 可 | 想定外 | 想定外 | 想定外 | 想定外 | 想定外 | 想定外 | 想定外 | 想定外 |
| 特定技能 | 1号で可 | 2号で可 | 2号で可 | 2号で可 | 2号で可 | 2号で可 | 2号で可 | 2号で可 | 2号で可 |
| 身分系ビザ (永住・定住・配偶者) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 特定活動9号 (インターン) | 条件付で可? | 条件付で可? | 条件付で可? | 条件付で可? | 条件付で可? | 条件付で可? | 条件付で可? | 条件付で可? | 条件付で可? |
※インターンシップについては、あくまで海外の大学と提携したプログラムであり、その趣旨を逸脱しない範囲での就労が認められると考えられています。
このように、主に現場作業員を募集する場合には、特定技能、技能実習、身分系(永住者、定住者、配偶者ビザ等)のビザとなります。
一方で、施工管理などいわゆるホワイトカラー職種で募集する場合には、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号のビザとなります。

特定技能で受け入れる方法
現場作業員が不足する企業の場合は、特定技能での受け入れがおすすめです。
特定技能外国人を受け入れるながれはいかのとおりとなります。
①建設業許可の取得
500万円未満の工事の場合、建設業許可は不要であることから、許可を取っていない事業者さまも多いのではないでしょうか?
しかしながら、特定技能外国人を雇用するためには、建設業許可を取得しなければなりません。
なんらかの建設業許可を取得していれば、特定技能外国人を雇用することは可能です。
②建設キャリアアップシステムの登録
事業者登録及び外国人技能者、両方の登録が必要です。
建設キャリアアップシステムについては、こちらをご確認ください。
③JACへの加入
一般社団法人「建設技能人材機構」通称JACに加入する必要があります。
加入方法は、①JACへの直接加入、②正会員の傘下に加入、の2パターンがあります。
詳細は、こちらのJACのHPをご確認ください。
JACへの加入が完了したタイミングで、外国人の募集を開始するのが良いです。
④建設特定技能受入計画の認定申請
外国人と面接を実施し、無事雇用契約を締結したら、次のステップです。
建設業で特定技能外国人を受け入れる場合には、国土交通省に建設特定技能受入計画というものを提出し、認定を受けなければなりません。
チェックされる項目としては、報酬が日本人と同等以上か、月給制で給与支払う契約になっているか、日本人の募集をしても集まらないという状況か、などが上げらられます。
必要書類も多く非常に面倒な手続きですので、自社するのではなく、行政書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。
⑤出入国在留管理庁への申請
国土交通省からの認定がおりたら、出入国在留管理庁へ申請をします。
国外の外国人を採用する場合には、許可が出るまで概ね3ヶ月程度、国内の人材を採用する場合には2ヶ月程度と言われています。
もっとも、ケース・バイ・ケースですぐにこれよりも早く許可がでる場合もあれば、そうでない場合もあります。
登録支援機関との契約
特定技能外国人を雇用する場合には、受入れ機関は、日本で特定技能外国人が不安なく生活を送れるように以下の支援を行う必要があります。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援
10.定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援を自社で行うためには、過去に外国人を受け入れたことがあるか、もしくは外国人のサポートを行ったことがある職員が社員としている必要があります。この条件を満たさない場合には、自社で支援を行うことができず、登録支援機関へ支援の委託をしなければなりません。
なお、特定技能外国人を受け入れる方法については、以下の記事で解説しておりますので、あわせてご確認ください。

技能実習で受け入れる方法
つづいて、技能実習で外国人を受け入れる方法についてみていきます。
技能実習生の場合も、建設現場で労働することが可能となっています。
監理団体への加入が必須であることが、特定技能と異なる大きな点です。
技能実習の仕組み
技能実習は、以下のような仕組みになっております。

受け入れ方法(企業単独型・団体監理型)
まず、受入方法については、上図のとおり、①企業単独型と②団体監理型の2つがあります。
①企業単独型は、海外に設立した工場で勤務する外国人を日本の工場に呼び寄せるイメージで、大企業に多い形です。
②続いて、団体監理型について、監理団体を通じて外国人を呼び寄せる方法で、ほとんどの企業がこの形で技能実習生を日本に呼び寄せています。
団体監理型の仕組みと受け入れまでの流れ
団体監理型で技能実習生を呼び寄せる場合に、必要になってくるのが、①監理団体と、②送り出し機関です。
①監理団体とは、技能実習生の生活を支援する機関です。
基本的にこの監理団体が、以下で説明する送り出し機関との調整を行い、日本に技能実習生を連れてきます。
②送り出し機関とは、技能実習生を海外から日本に連れてくる海外窓口です。
技能実習生を雇用するための流れは以下のとおりです。
| ①技能実習生を受入れしたい企業が監理団体へ申し込みを行います。 ②監理団体は既に契約を締結している送り出し機関と調整し、企業がほしい人材の選定を依頼します。 ③海外現地またはオンラインにて、送り出し機関が集めた人材の面接を行います 面接は、監理団体と受入れ企業が一緒に行うが一般的です。 ④人材が決まれば、受入れ企業と人材とで雇用契約を締結します。 ⑤受入れ企業側で、技能実習の実習計画の作成を行い、外国人技能実習機構へ、申請をします。 ⑥実習計画の許可を受けることができれば、出入国在留管理局へビザ申請します。 ⑦ビザの許可がおりたら、外国から外国人を呼び寄せます。 ⑧入国後、監理団体にて2ヶ月または1ヶ月の講習を実施します。 ⑨講習後、労働が開始します。 ⑩監理団体は、受入機関が計画通りに実習を実施しているか適宜確認します。 |
建設業で受入れ可能な職種
建設業での対象職種・作業は、22職種・33作業です。各職種で作業内容が決まっており、基本的に実習生は現場での作業に従事します。
必要な要件
建設業で技能実習生を受け入れる場合には、受け入れ事業者が以下の要件を満たす必要があります。
| ①欠格事由に該当しないこと 過去に入管法等の法令により、処罰を受けていないことや、暴力団関係者ではないことが求められます。 ②実習責任者、実習指導員、生活指導員を選任すること ③実習生の住居を確保すること 相部屋でも問題ありませんが、1人あたりの専用スペースが4.5㎡必要です。 ④社会保険へ加入すること ⑤監理団体へ加入加入すること ⑥建設業許可を取得すること ⑦建設キャリアアップシステムに登録すること ⑧実習生の人数が、常勤職員数を超えないこと |

技術・人文知識・国際業務及び特定活動46号で受け入れる方法
ここでは、技術・人文知識・国際業務及び特定活動46号で受け入れる方法についてみていきます。
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務というビザは、いわゆるホワイトカラー職種のためのビザで、国内外問わず大学を卒業した外国人の方向けのビザと考えられています。
このビザでで想定されている業務は、以下のとおりで、「単に知識が必要というだけでは足りず、大学や専門学校などで学ぶ学問としての体系的な知識が、その業務を行う際に求められたり、業務パフォーマンスを向上させたりする程度の業務」が想定されています。
技術・人文知識・国際業務
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
つまり、このビザで働くことができる業務は、「学問的な知識を必要とする業務」で、日雇い労働者やアルバイトが行うことができる、現場作業は含まれておりません。
施工管理の業務として求められる能力は、まさに学問的な知識を必要とする業務であることから、この「技術・人文知識・国際業務」というビザで、施工管理の業務に従事することが可能となっております。
しかしながら、前述のとおり、原則現場作業には従事できません。もっとも、現場作業にも多種多様なものがあること、日本人の施工管理技士でも現場作業を行う場合があること、から絶対に従事できないとは言い切れないことから、どのような作業であれば可能かどうかは、学問的な知識が必要かどうか、という観点から考えて判断することが必要になってきます。
さらに、施工管理として採用した日本人の新入社員を、研修の一環として現場作業に従事させるということをキャリアプランとして明確に定めている企業の場合には、外国人においても同様に、研修期間は現場作業に従事できる可能性があります。
この研修期間については、ビザ申請の際に出入国在留管理庁に文章で説明しておく必要があり、それを欠いて、研修として現場作業に従事させた場合、不法就労助長罪として罰せられる可能性があるので、注意が必要です。
このように、技術・人文知識・国際業務というビザで外国人を雇用する場合、慎重に出入国在留管理庁へ申請する必要があります。
特定活動46号
続いて、特定活動46号について説明します。このビザは、日本の大学を卒業し、かつ日本語能力N1以上のレベルを有する外国人のためのビザとなっております。
上で説明した「技術・人文知識・国際業務」では、原則現場作業に従事することはできませんが、この「特定活動46号」では、業務で通訳をすることを前提に、施工管理業務はもちろんのこと、現場作業に従事することが可能です。

どのビザで受け入れるのがおすすめ?
結局どのビザで外国人を雇用するのがおすすめか?
それは、技術・人文知識・国際業務と特定技能のハイブリッド方式でしょう。
まず、施工管理人材を雇用することで、登録支援機関を使わずに特定技能外国人を雇用することが可能となります。
そして、特定技能外国人の面接の際には、当該施工管理人材に立ち会ってもらい、同じ国籍の人間として問題ないか判断してもらいます。
また、日本語能力がN4以上あるとはいえ、危険の伴う現場ではやなり、母国語で指示をした方が安全に作業を実施することが可能です。
以上から、日本語能力に堪能で技術力のある、施工管理人材をまず雇用し、その後、特定技能人材を雇用することをおすすめします。

まとめ
今回は、建設業で外国人を雇用するための方法について説明してきましたが、いかがでしたか?
弊所では、外国人雇用に関する相談を無料で実施しておりますので、ぜひご連絡ください。